都会の真ん中に生まれた虚しいサガ、深川はつまらない街⁈

俺は深川の生まれの江戸っ子だ⁈⁈文句あっか!!
それにしても、「俺は深川の生まれの江戸っ子だ」と虚勢を張ったのに、深川がつまらない街とは一体どういうことなのでしょうか。
深川と言うと世間一般が思い浮かぶのが、時代劇に出て来る貧しいながらも人情味に溢れた粋な長屋の風景や芸者がいて芭蕉のお気に入りの世界ですよね。
ところが当時の深川地区は確かに人は多いが、あちこちから流れてきた人でごった返す寄合所帯の街だったので活気だけはあったのです。
だが、街中が汚らしくゴミゴミしていただけの貧民街そのもので、人情味や粋な感じなどはゼロだったのです。
人の洪水が押し寄せた深川の街
そう、当時の東京の下町地区は、全国から人の洪水が押し寄せて、街はパンク状態と化していたのです。
その情景は、人口過密のバングラデシュを彷彿させるほどでした。
特に深川地区は、日本橋、茅場町や大手町などの開発初期のオフイス街と目と鼻の先という利便性があったことで、戦後になって他からの流れ者が一気に住み出した地域なのです。
当時はとにかく、住宅事情が最悪だったので、一軒家に二家族三家族が住むのが当たり前の世界で、殆どの人間が仮住まいの存在です。
それこそ、生粋の江戸っ子などと言う人は3割程度しか住んでいない街なのです。
狭い町内は寄せ集めの田舎者ばかりなので、人間関係は人情味とは裏腹のぎすぎす状態、朝から晩まで住民同士の口論が絶えなかったのです。
早い話が住んでいる人間は全国各地から集まった地方出身者ばかりなので、連帯感も無く愛着を持って住んでいる人など殆どいないということです。
そんなこんなで、高度成長期と共に、今度は都下の周辺地域でニューシティが続々と開発されたことで、この狭い空間から脱出しようと、瞬く間に人口が消えて行ったわけです。
一応、都会なので過疎化にはならないが人が出て行く一方の街なので、見る見る活気が萎んで行き街は廃れていったという感じです。
そんな寄せ集めの場所では思い入れも何もあったものではない。
私も小学5年で深川を後にした脱出組の一人、喧噪状態の深川からヘビだらけのど田舎の多摩に引っ越したのです。
江戸三大祭りで有名な深川ですが、よくよく考えてみれば神輿を担いでいたのは江戸っ子では無く倉庫の季節労働者か田舎の人間ばかりなのです。
これが深川の風物詩なのです。
これではいなかっぺ野郎と喧嘩にもなりゃしない。
今日はここまでとさせて頂きます。
明日も残念な街、深川の話パート3です。

 忍者ライターの久保誠が「デュラルライフ」「田舎暮らし」「シニアライフ」「スローライフ」「海外ロングステイ」の情報と「雑学のすすめ」を主題として、ソフトタッチに日々の出来事、経済、国際情勢、政治、芸能、歴史のウンチクなどを語ってまいります。
忍者ライターの久保誠が「デュラルライフ」「田舎暮らし」「シニアライフ」「スローライフ」「海外ロングステイ」の情報と「雑学のすすめ」を主題として、ソフトタッチに日々の出来事、経済、国際情勢、政治、芸能、歴史のウンチクなどを語ってまいります。
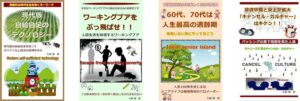




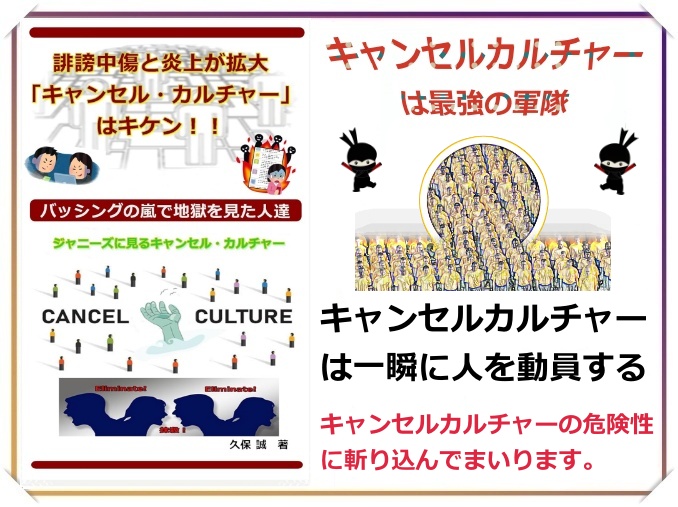


コメント