交換様式となってしまった田舎移住の現実

一極集中の打開策として、地方創生の鳴り物入りではじまった田舎暮らしでしたが、移住者と受け入れ側のボタンの掛け違いによってトラブルだらけの修羅の展開を呈してしまった感もあるのでした。
その要因の最たるものは田舎の凝り固まった閉鎖性に尽きるのです。
それを助長させているのが国による丸投げの悪しき体質なのです。
ということで今回は、田舎の悪しき風習である歪んだ閉鎖性に視点を置き、その精神を作り上げる根源を簡単判りやすく説明してまいります。
田舎の閉鎖性を作り上げる独善的精神
この田舎の凝り固まった閉鎖性という連帯精神のエンゲージメントは一体どこからくるものなのでしょうか。
それは田舎特有の旧態依然の伝統的な組織の文化が存在することに起因するのです。
誰もがこんな伝統や習わしは今の時代にはそぐわないと思っていても、田舎の場合は、人の気持ちよりも独善的精神を持って人間の行動を押さえつけてきたのです。
この歪んだ独善的精神こそが、若者の田舎離れを加速させ、田舎のイメージを大きく停滞させて行ったのです。
田舎の長老たちには、集落の未来を読む力がないので、集落の利益がどこにあるかも理解出来ていないのです。
そんな連中に翻弄されては堪らないと田舎の若者たちさえも一目散に逃げだしたのです。
結局、国や地方自治体が主導する田舎への招致は、出て行ってしまった田舎の若者の代わりに都会の若者を招致するという、交換様式となってしまった感があるのです。
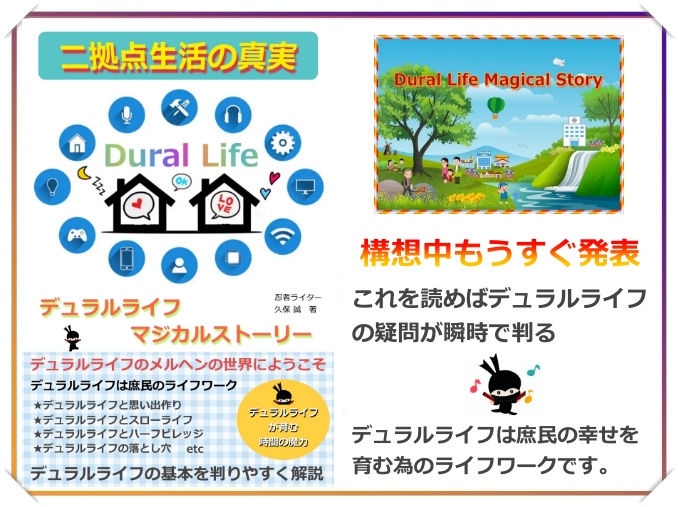
「カリブの楽園」への招致の騙し討ちの再来
しかしながら、そんな独善的精神の塊の中に交換様式として都会の人間を当て嵌めようと企む国や地方自治体の根性は、かつて国民を騙し討ちにした「カリブの楽園」ドミニカ共和国へようこその、「ドミニカ移民の悲劇」と被るところがあるのです。
国が国民を騙し討ちにした「ドミニカ移民の悲劇」の詳細に関しては、またの機会にご説明することとしますが、それにしても、この交換様式も眉唾もいいところです。
交換様式とは、本来はフィフティーフィフティー、ウインウインでなければならないものです。

先住者は関取、移住者はどんなに頑張っても三段目止まり
ところが、田舎の場合は、「受け入れてやる」の一点張りなので、始めから主従の関係が築かれた状態なのです。
これでは、自分たちの都合のいいように下働きをする人間を求めているに過ぎないのです。
こうして、交換で来た都会人は下働きを担うカーストの末端に組み込まれ奴隷となって行くのです。
どんな環境でも一端、築かれてしまった上下の関係を逆転することは並大抵のことではないことは誰もが知ることです。
田舎の集落の場合は、先住者は関取、十両の地位、50年前に移住してきた人間でも幕下止まり、都会からの移住者はふんどし担ぎの身分から始まり三段目止まりなのです。
そんなところでいくら頑張ったところで、三段目あたりで嫌がらせを受けてしまい、ポシャらされるだけなのです。
田舎を真っ向から否定する話ばかりとなってしまいましたが、この有様では、彼らの性根が変わらない限りは如何ともしがたいと言うしかありません。
金だけばら撒いて好き放題にさせているからこんな惨状となるのです。
今日はここまでとさせて頂きます。

 忍者ライターの久保誠が「デュラルライフ」「田舎暮らし」「シニアライフ」「スローライフ」「海外ロングステイ」の情報と「雑学のすすめ」を主題として、ソフトタッチに日々の出来事、経済、国際情勢、政治、芸能、歴史のウンチクなどを語ってまいります。
忍者ライターの久保誠が「デュラルライフ」「田舎暮らし」「シニアライフ」「スローライフ」「海外ロングステイ」の情報と「雑学のすすめ」を主題として、ソフトタッチに日々の出来事、経済、国際情勢、政治、芸能、歴史のウンチクなどを語ってまいります。
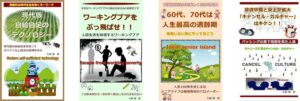



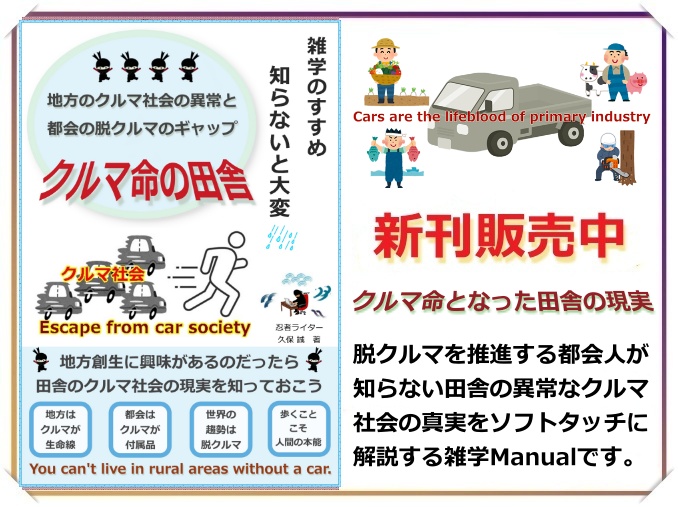


コメント