南国土佐の悪代官パート4:告発の虚しさ

今日も引き続き土佐の田舎で起きた騒動の真相に迫ります。
この告発は、一般大衆を巻き込み、それ相当な反響と支持を受けたことは事実のことです。
だが、冷めたことを言うのも何ですが、これらの支援は得をするような救済には繋がらないという大いなる矛盾ともいえる告発の虚しさがあるのです。
何とも不条理な言い回し方ですが、ここは、傍若無人を振り撒く先住者の地盤でありベースであるということです。

よそ者は身を引くしかないという虚しい現実
しつこいくらいに毎度同じことを言ってしまいますが、よそ者の移住者が田舎という閉鎖的なベースで主役を張ることは出来ないのです。
だから、理不尽だが、相手と喧嘩となってしまったら、そこを出て身を引くしかないのです。
何と言っても、日本の場合は、まだまだ内部告発を社会正義と捉える風習がないことで、場合によっては軋轢を生んでしまいかねないのです。
それにしても、このやり方は、腹いせだけだったら、してやったりの大正解の展開だったことは確かなことです。
だが、ちょっと不味かったのは、これによって市の対応に対する問題や地元そのものの評判も同時に落としてしまったことで、市民とも軋轢を生んでしまう結果となってしまったからです。
そこまでなってしまうと、もうここにはいられないということになるのです。
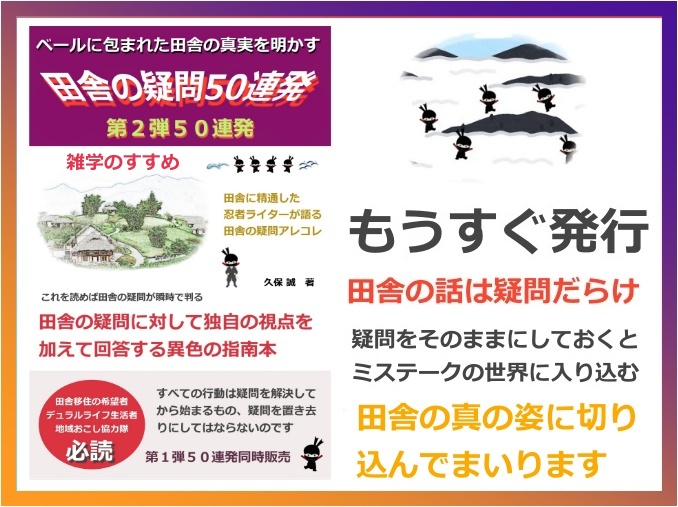
SNSの拡散は思いもよらない展開を巻き起こす
とにかく、SNSの怖いところは、不特定多数の人間を巻き込んでしまうことで、予期せぬところに煙が立ってしまうということに繋がってしまうからです。
そう、もうこうなるコントロールは不可能となるので、まったく意図しない方向へと向かい出してしまうのです。
この騒動によって、市役所には爆発予告のメールが届き、市の幼稚園には子供を誘拐するなどという物騒なメールが届いたりで、こうなると告発者こそが市民の敵という状態となってしまうわけです。
残念なことですがこのやり方だと、知らない人からは支持を受けても、そこに住む人からは逆に筋違いの憎悪を生んでしまいかねないのです。
多くの人は告発者に共鳴して声を挙げてくれたことは確かですが、ごく一部には、こうした騒動に便乗するヤカラが必ず出てくるのです。
この対立は双方、弁護士に依頼してのものだそうですが、ここまで市や市民を巻き込んではこの地で商売することなどはもはや無理というものです。
この騒動の舞台となった観光交流施設、そもそもこの事業形態自体が営利商売を行なうにはあやふやなもので、契約書もまともに交わしていなかったようなのです。
だが、頑張って店を流行らせたオーナー側には従属的立場ゆえそれほど落ち度はないが、問題は市や指定管理者であるNPO法人の対応なのです。
今日はここまでとさせて頂きます。
明日は、炙り出されてきた不適切な交付金の実態について迫ります。

 忍者ライターの久保誠が「デュラルライフ」「田舎暮らし」「シニアライフ」「スローライフ」「海外ロングステイ」の情報と「雑学のすすめ」を主題として、ソフトタッチに日々の出来事、経済、国際情勢、政治、芸能、歴史のウンチクなどを語ってまいります。
忍者ライターの久保誠が「デュラルライフ」「田舎暮らし」「シニアライフ」「スローライフ」「海外ロングステイ」の情報と「雑学のすすめ」を主題として、ソフトタッチに日々の出来事、経済、国際情勢、政治、芸能、歴史のウンチクなどを語ってまいります。
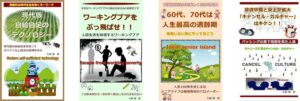



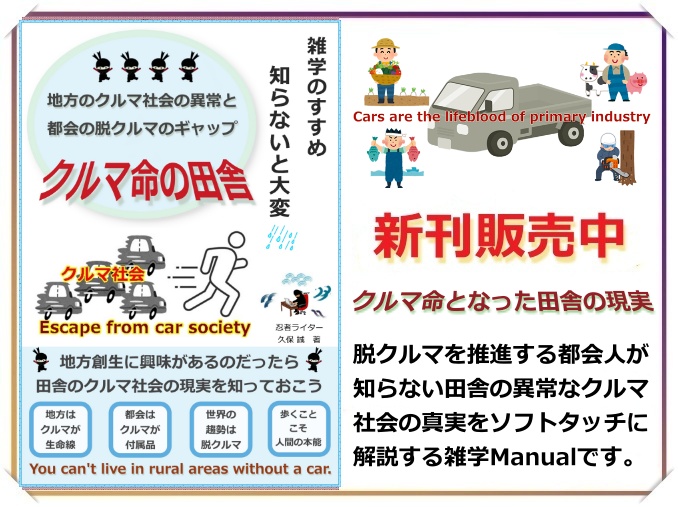


コメント