地域おこし協力隊関連のトラブル「別子山」パート3

それでは今日も昨日に続き別子山の田舎暮らしトラブルで浮かび上がってくる地方創生事業のまやかしの実態を簡単判りやすく解説してまいります。
余興で税金を食い尽くす地方創生の実態
田舎は古いしきたりの伝統によって秩序が守られているのです。
しかし、困ったことは税金が賄われているNPO法人にもその伝統やらが継承されていることなのです。
ここで、問題となった「別子山地域の未来を考える会」というNPO法人ですが、この団体のメイン活動は、カエデの栽培でメープルシロップを作るという特産品づくりで若者の雇用に結びつけるという構想のようなのです。
しかし、この構想は10年経っても採算の見通しはまったく立っていないという絵物語と化しているのです。
10年経っても採算のメドはたっていないとなると、支出だけとなるので事業の撤退か別案での再構想の話となるのが普通のことです。
ということは、「別子山地域の未来を考える会」のこの事業には税金が投入されているということなのでしょうか、まさか民間企業であればこんな無駄な真似をする筈はありませんよね。
それにしてもこんなレベルのものでは大したお金の投資は無いことでしょうが、国や町などからお金が降ってくるので切羽詰まった感はまるでないということです。
そう、人の金で動かしていることなので、結果が出せなくとも何でもないのです。
自分のお金で動かしていたとしたらこんなバカをやらかす筈はないですよね。
それにしても10年ですか、のんびりゆったりでいいですね。
これを聞いて、マスコミや不動産屋がいう田舎でのんびりゆったりのスローライフ生活を送りましょうという定番の宣伝キャッチを思い出しちゃいました。
あらら本当にスローライフ生活が出来たんだ、それも税金で。
地方創生事業の実態なんて、どこもこんなもの、やる気も気迫も伝わってこないのです。
NPO法人などは名ばかりで、早い話が税金を食い物にしていると言うことです。
「地域おこし協力隊」の任期は3年余り、こんな先の見えない絵物語では、本腰を入れようという気力も萎えてしまうのはよく判ります。
まあ、どんな世界でもそうですが、後から来たら主従関係というものが出来てしまうので、それに従う以外に無くなってくる。
この告発によって、愛媛県の新居浜市と別子山地区のイメージは大打撃となってしまったようですが、そもそも変わる気のない、変わろうともしない地域に税金を投入することは無駄でしかないのです。
このケースは、お金を投資したところで遊びの余興に消費されてしまうのが関の山という現実がよく判りましたよね。
新居浜市と別子山はもろにそれを全国にさらけ出してしまったのです。

 忍者ライターの久保誠が「デュラルライフ」「田舎暮らし」「シニアライフ」「スローライフ」「海外ロングステイ」の情報と「雑学のすすめ」を主題として、ソフトタッチに日々の出来事、経済、国際情勢、政治、芸能、歴史のウンチクなどを語ってまいります。
忍者ライターの久保誠が「デュラルライフ」「田舎暮らし」「シニアライフ」「スローライフ」「海外ロングステイ」の情報と「雑学のすすめ」を主題として、ソフトタッチに日々の出来事、経済、国際情勢、政治、芸能、歴史のウンチクなどを語ってまいります。
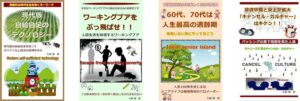



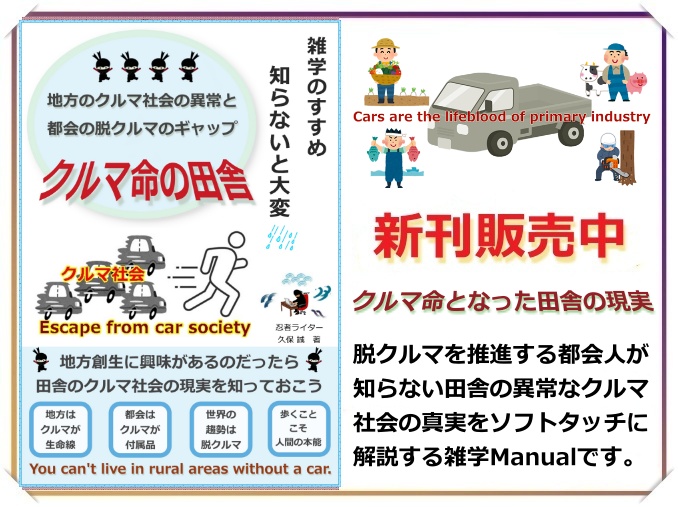


コメント