地域おこし協力隊関連のトラブル「別子山」パート2

それでは今日は別子山のトラブルについて書いてまいります。
今回取り上げるこのケースも、田舎暮らし騒動の典型例といえるもの、双方の言い分が平行線を辿るばかりなので、話がまったく噛み合っていないのです。
田舎側の持論としては、勝手に出て行ったのに、自分のうっ憤や腹いせをネットに晒すなどは卑怯だというわけです。
それにしても、この告白は勇気ある決断だった、田舎暮らしの実態が白日に晒された意義はとても大きいからです。
どうせ相手は真っ向から反論してくるので、中途半端な緩い言い回しは逆効果なのです。
事実のことを話せばいいし、ストレートに自分の思いを証言するのは当然のことです。
これぞ田舎暮らしの実態
これは、双方が嘘をついていると言うことは殆ど無く、互いが正論を言っているに過ぎないのです。
これこそが田舎暮らしの一番怖いところなのです、それだけ隔たりがあり、埋めようもないギャップがあると言うことです。
これでお判りの通り、これは、この地域だけの問題ではなく、国家の莫大な税金を消費する地方創生事業のあり様を問う話なのです。
総務省が莫大な血税を投資して鳴り物入りで事業化した「地域おこし協力隊」という存在。
現在、「地域おこし協力隊」の隊員は、全国各地に6000人規模の人員を配置しているのです。
ところが、その実態はというと、総務省は金をばら撒くだけで、地方自治体、市町村への丸投げという地方任せの状態なので、地域によっては「地域おこし協力隊」としての機能がまったく活かされていないのです。
結局、役所のやることは丸投げの連鎖となってしまい役場と地元住民との意思の疎通も図れていないことでギャップを生んでしまうのです。
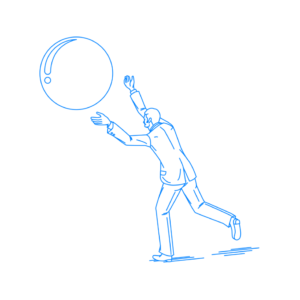
そんな状況の中に隊員が送り込まれてもモチベーションを発揮する場など殆どある筈は無いのです。
今回のケースもまったくこれと同じ、役場は役場で住民団体に丸投げしているのでこうしたミスマッチだらけとなってしまうのです。
それにしても、年寄りばかりの過疎化の田舎でYouTubeで生計を立てるとなると、周りからは殆ど理解されないでしょう。
この主人公曰く、「私と妻の大人だけであれば残る選択肢もあったが、一部の人と人間関係が険悪になってしまった中で、子育てをしていくこと、妻も産後間もなかったのでケアしながら向き合っていく気力がなかった」と語っているのですが、これはもはや地獄の入り口に入ってしまったと言っていい状況です。
逃げて大正解、夫婦だけでも針の筵なのに、子供がいたのでは最悪です。
今日はここまでとさせて頂きます。
明日もこの続きです。

 忍者ライターの久保誠が「デュラルライフ」「田舎暮らし」「シニアライフ」「スローライフ」「海外ロングステイ」の情報と「雑学のすすめ」を主題として、ソフトタッチに日々の出来事、経済、国際情勢、政治、芸能、歴史のウンチクなどを語ってまいります。
忍者ライターの久保誠が「デュラルライフ」「田舎暮らし」「シニアライフ」「スローライフ」「海外ロングステイ」の情報と「雑学のすすめ」を主題として、ソフトタッチに日々の出来事、経済、国際情勢、政治、芸能、歴史のウンチクなどを語ってまいります。
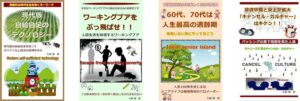
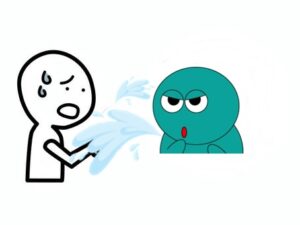


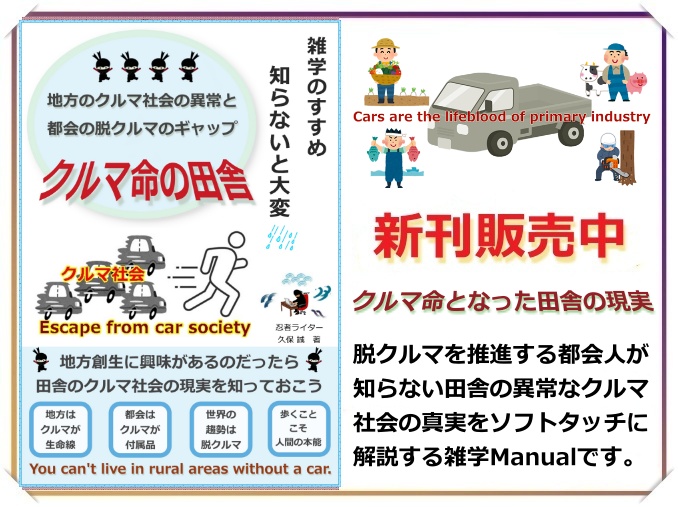


コメント