地域おこし協力隊関連のトラブル「別子山」パート1

昨年来、田舎暮らしのトラブルケースが次々と表面化していますが、このような問題は今に始まったことではなく、もうずいぶん前から取り沙汰されてきた話なのです。
ということで今回は、憧れだった田舎暮らしが一転、失敗のトラブル続きとなってしまった実態をYouTubeで発信して話題となった「元地域おこし協力隊」の隊員だった方の話を中心に簡単判りやすく話をまとめてみました。
この一件も、古い話となってしまいましたが、簡単に風化させてはならないものなので、警鐘を促す意味で改めて検証してみたいと存じます。
この話は急迫したものではないので、4回にわたって周辺のあらましを含めて紹介します。
初回は、地域おこし協力隊のあらましを簡潔に紹介することに止め、明日から本題に入ってまいります。
この主人公の方は、教員の仕事を辞め、都会から過疎化が進む愛媛県の別子山に移住して、夢だった田舎暮らしの生活ぶりを発信していたのです。
それが、予期せぬトラブルに見舞われてしまい、もう限界とばかりに、一気にネガティブキャンペーンの発信へと変貌してしまったのでした。
ここから始まった移住者の反撃、行政への対応の不審や地域団体との軋轢、そして嫌がらせなどのトラブルをYouTubeで発信したことで大反響となったのです。
この一件を聞くにつけ、移住者の立場の弱さがクローズアップされたことで、田舎暮らしの切なさと虚しさを彷彿とさせる展開へと相成ったのでした。
地域おこし協力隊員の虚しい志
実は、地域によっては「地域おこし協力隊」の存在は超の付いた軽量級もいいところ、税金で暮らす甘ちょろの身分とされ、ただのパシリの存在としか捉えられていない場合もあるのです。
このケースの場合を見ると、役所と住民の対応も、モロにそれに当て嵌まっていると言っていいでしょう。
地域おこし協力隊の隊員の方は、自らの力で田舎を変えたいという願望を持つそれなりの志を持った方ばかりなのです。
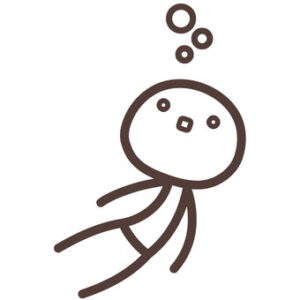
しかし受け入れ側の思惑とはマッチしないことで、せっかくのスキルが活かせないままの方が非常に多いというわけです。
結局、受け入れ側は、地域おこし協力隊の隊員にそこまでの役割を求めてはいないということなのです。
同じことを何度も言ってしまうのですが、地域おこし協力隊の場合は、隊員の箔付けといえる資格の検定などがなされていないことで、存在自体が軽薄な扱いにされがちとなってきてしまったのです。
地域によっては受け入れ側の計画設定が曖昧なことで、地域おこし協力隊員に何を依頼したらいいか持て余した状態となっている場合もあったりで、アンマッチが繰り広げられているのです。
まあ、この話をすると長くなるので、またの機会にお話するとします。
それでは、明日からこの話の本題に入ってまいりますのでよろしくお願い申し上げます。

 忍者ライターの久保誠が「デュラルライフ」「田舎暮らし」「シニアライフ」「スローライフ」「海外ロングステイ」の情報と「雑学のすすめ」を主題として、ソフトタッチに日々の出来事、経済、国際情勢、政治、芸能、歴史のウンチクなどを語ってまいります。
忍者ライターの久保誠が「デュラルライフ」「田舎暮らし」「シニアライフ」「スローライフ」「海外ロングステイ」の情報と「雑学のすすめ」を主題として、ソフトタッチに日々の出来事、経済、国際情勢、政治、芸能、歴史のウンチクなどを語ってまいります。
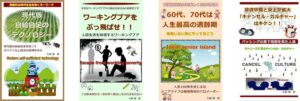



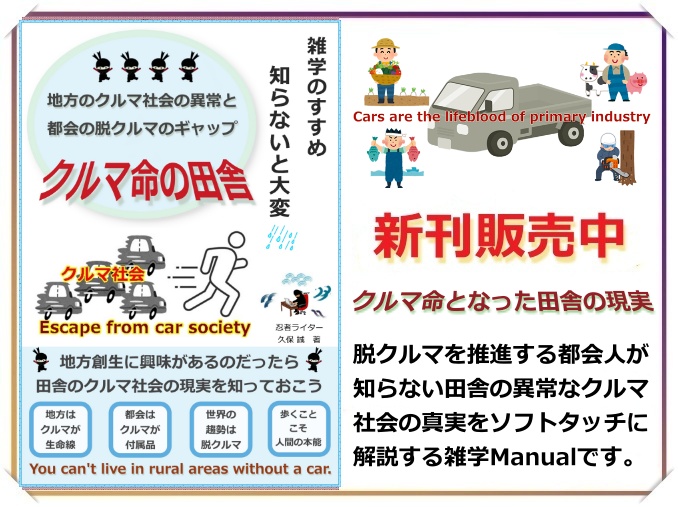


コメント