ヨーロッパに学ぶグローバリズムの過ち

外国人問題で揺れ動く日本の場合、ヨーロッパ社会で巻き起こっている反グローバリズムの流れを読み解いておかねばならないのです。
しかし何度もご指摘する通り、日本の場合、完全に偏ったオールドメディアの偏向報道によって、多様性一辺倒となり、その実態が覆い隠されてしまっているのです。
そうした中で今回は、ヨーロッパ社会の移民の模範のモデルだった旧来の移民たちの葛藤模様などに迫り、ヨーロッパ社会の実情をいつも通りの雑学タッチで簡単判りやすくご説明をしてまいります。
移民を無尽蔵に入れたリベラルの過ち
移民に対して寛容に接する移民政策の優等生であるヨーロッパ社会、その伝統あるヨーロッパ社会の移民政策がここに来て崩壊の兆しが見えてしまったのです。
いや、もはやそのレベルではない、著しい秩序、道徳の低下と治安の悪化を招き、挙句の果てにはヨーロッパ社会で最も重要な価値観であるキリスト教文化が破壊されかねない事態となってしまったからです。
これは急ぎ過ぎたグローバリズムの流れからくるもので、ヨーロッパ社会もご多分に漏れず、少子高齢化によって人手不足の状況となってしまい、その人手不足を補う為に期待されたのが移民たちだったというわけです。
ところがまさかの事態、今の移民たちは、どんなに優遇措置を施し寛容に接してもヨーロッパ人の思惑に当て嵌まる従順な存在ではなかったのです。
こんな筈ではなかった、完全に思惑外れとなってしまったヨーロッパの国々、しかし、一端移民を入れてしまったら最後、追い出すわけにもいかなくなってしまったのです。
戦後の移民とは別人種だった現代移民の存在
ヨーロッパの国々は何故、移民に対する寛容政策をとったのでしょうか。
それは、戦後に移住してきた移民たちの勤勉性を見てきたからです。
戦後に出稼ぎ目的でヨーロッパ各国に移住してきた外国人の多くは、それぞれの新天地で国や国民に認められ、それなりに生活の基盤を築いて安泰な日々を送ってきたのです。
その当時の移民は、異国の地に同化して行く為には働き者という勤勉であることが最低条件だった筈なので、言葉の不自由さゆえに、差別の対象となったりと、それ相当な四苦八苦な奮闘があったことが窺い知れるわけです。
何と言っても、当時のヨーロッパは、植民地支配の名残が色濃く残る閉鎖的な社会であったことで、異種民族に対する差別感情が燻っていたのです。
しかし当時の移民たちは、そんな状況下にあっても持ち前の奮起と努力でそれを克服して乗り切ったというわけです。
そんなことで、彼らの多くはヨーロッパ社会のキリスト文化に溶け込む為に母国の文化を捨てヨーロッパ人になりきったということです。
グローバリズムが旧来移民の生活を脅かす
しかし、グローバリズムの流れによって、彼らが必死に築いて来た礎を崩壊させてしまったのです。
新しい移民たちによってヨーロッパ各国で巻き起こされた暴動やテロ行為、それに反発する各国国民の移民排斥の嵐、旧来の移民たちはその反動をもろに受けることになってしまったのです。
国民対移民の争い、キリスト教徒とイスラム教のせめぎ合い、ヨーロッパ社会はもはや殺伐化した雰囲気となってしまい、完璧なまでにヨーロッパ社会に溶け込んだ筈の旧来の移民たちは、移民排斥のスケーブゴートに晒される羽目となってしまったのでした。
そう、こんな筈ではなかったという思いは、ヨーロッパ人だけではなく、旧来の移民たちも感じたこと、今の移民は、我々とは完全に人種が違うという余りのギャップ。
やはり、時代の流れと言うものは大きい、今の移民の中には、同じイスラム教徒でも、過去にはなかったイスラム国やシーア派やタリバンなどのイスラム原理主義という民主国家の社会通念では理解し難い過激な宗教思想を持った人物たちが多いのです。
そんな過激な思想を持った移民たちに対して多文化共生などのおとぎ話の言葉は、言語道断のものとなって行ったのです。
今のアラブ人や黒人たちは移民であろうと、昔と違って、白人に対して従順ではないということなのです。
これはグローバリズムを推進するリベラル層がそうした背景を理解しないで、後先を考えず、見境なく移民を大量に受け入れてしまったというミスマッチそのものなのです。
しかしながら、グローバリズムを推進するリベラル層は、自分たちの過ちを認めようとはしないので、未だに移民政策の推進こそが、多文化の共生であるという妄想を唱えているのです。
日本は島国国家、綺麗ごとで人を受け入れてしまったら取り返しのつかないことになってしまうことでしょう。

 忍者ライターの久保誠が「デュラルライフ」「田舎暮らし」「シニアライフ」「スローライフ」「海外ロングステイ」の情報と「雑学のすすめ」を主題として、ソフトタッチに日々の出来事、経済、国際情勢、政治、芸能、歴史のウンチクなどを語ってまいります。
忍者ライターの久保誠が「デュラルライフ」「田舎暮らし」「シニアライフ」「スローライフ」「海外ロングステイ」の情報と「雑学のすすめ」を主題として、ソフトタッチに日々の出来事、経済、国際情勢、政治、芸能、歴史のウンチクなどを語ってまいります。
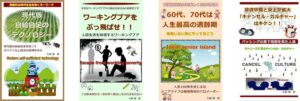



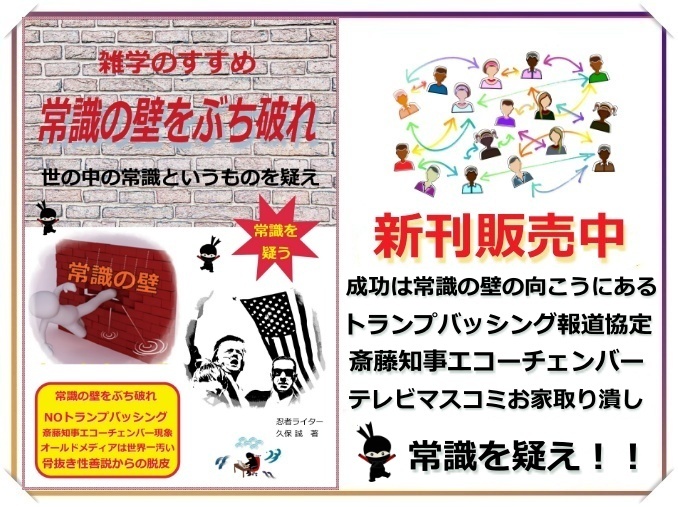
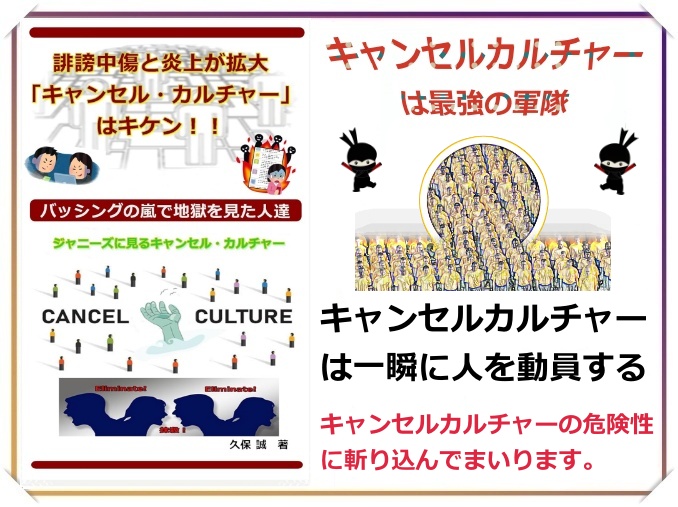
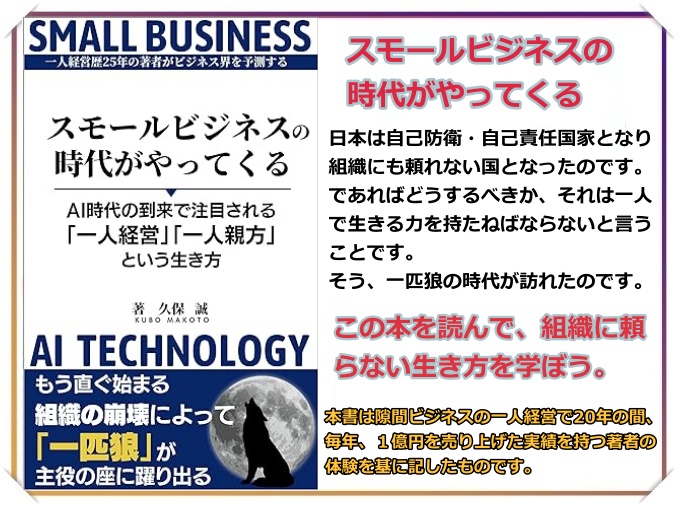


コメント