SNSを規制したネパールは国家崩壊の危機

日本でSNSなどのソーシャルメディアを規制しようという動きがある中で、実際にSNSを規制したネパールでは、Z世代の大暴動が起きてしまったのです。
この暴動によって、19人が巻き込まれて死亡するという惨事に発展し、ネパールの国家機能が麻痺した状態となっているのです。
このネパールの大暴動は当然の帰結といえることでしょうね、それくらい、SNSなどのソーシャルメディアは世界中から信頼を集め、日常生活にも密着したものなので、もはや簡単には手放せない存在となっているのです。
とくにアジア最貧国のネパールの場合は、SNSなどのソーシャルメディアこそは唯一の国民の拠り所となっていたことで、その反発は予想以上だったということです。
そう、世界の流れはSNSなどのソーシャルメディアを中心に回っているというわけで、日本もこの真実を見極め、安易な判断は慎むべきなのです。
国はSNSに情報統制をかけようと必死
しかしながら、SNSなどのソーシャルメディアは、何故、目の敵とされるのでしょうか。
それは、SNSなどのソーシャルメディアの場合、一般大衆が瞬時で情報を知ることが出来、またそれを拡散することも出来てしまうので、情報を統制したい政府からは目の敵とされてしまうのです。
通常のマスメディアは体制とナアナアなプロの情報屋なのでアメを与えれば国に対して尻尾を振ってくるのですが、SNSなどのソーシャルメディアは、一般大衆が中心なので、そのままダイレクトに情報を流してしまうのです。
これはオールドメディアがカッコつけでのたまうファクトチェックとかの話ではなく、本物かヤラセかの違いなのです。
結局、政治絡みの世界では、新参物のSNSによって、利権絡みや談合体質などの腐敗構造なども暴かれてしまうことで、SNSなどのソーシャルメディアほど、邪魔なものはないのです。
まあ、何度も言いますが、SNSがなかったら、アフリカとのホームタウン認定のまやかしなどもバレずに済んだわけです。
だから、何としてでもSNSなどのソーシャルメディアを情報統制したいと考えているわけです。
そんなことで、日本の場合などは、オールドメディアやマスメディアを使って、SNSなどのソーシャルメディアの情報の過誤を指摘して批判と酷評を繰り返すのです。
日本は国とマスメディアが共同してSNSを潰しにかかる
ご承知の通り、SNSなどのソーシャルメディアは、情報を独占して来たオールドメディアやマスメディアにとっても脅威そのものなのです。
今迄、監視されることがなく、情報を一方通行で流しっ放しに出来たオールドメディアやマスメディアは、SNSの存在によって、一般大衆から瞬時に情報の真意が問われてしまい、やもすれば印象操作などの偏向報道も暴かれてしまうのです。
こうして、SNSなどのソーシャルメディアによってオールドメディアやマスメディアは自分たちの情報の既得権を奪われるはめとなって行ったことで、今度は財力を使ってグーグルやヤフーなどに参入してネット社会を牛耳ろうと画策しているというわけです。
ネパールの国の実態を全く知らない日本人
日本も対岸の火事ではないSNSの規制、それでは、SNSがきっかけで大暴動に発展したネパールという国について簡単に述べてまいります。
日本ではネパールというとヒマラヤ山脈のユートピアというイメージが強いのですが、実際のネパールという国は、国民の生活ぶりを見ると、救いようのないほどの格差拡大の貧困が喘ぐという、国民はその日暮らしを余儀なくされた国なのです。
そのメチャクチャぶりは、国中が汚職だらけで乱れ切った状態で、国の職員や警察も賄賂漬けとなっており、しかも麻薬が蔓延したカオスな国なのです。
そのカオスなネパールを支配しているのは中国寄りの共産党の政党なのでした。
そもそも、今回の暴動の発端は、腐敗したネパールの共産党政権を揶揄した情報がSNS上で拡散したことがきっかけで、それを共産党政府が規制したことで、大暴動へと発展してしまったのです。
まあ、これもいつも通りのことで、社会主義国家の運営が行き詰まってしまうと、どうしようもない腐敗構造が拡大してしまうのです。
そして、この国の宿命的な弱点は、高峰な山脈だらけなので、人が住める場所が極々限られた面積しかないので、人口が過密状態となっているからなのです。
そう、ネパールという国には平地が殆どなく、首都のカトマンズでさえ、標高1700メートルの地点にあるくらいなのです。
そうなると当然、農業には適さないし、製造業の芽も出ないというわけで、主要産業は観光産業くらいなのです。
これでは国民は夢も希望もない生活を余儀なくされてしまうのは当然のことですよね。
ネパール人は日本を目指す
今回のネパールの暴動が日本にとって、とても不味いのは、日本国が同じベンガル人のインド人とバングラデシュ人に対して移民を解禁したことが、ネパールにも伝わっていることなのです。
国民の知らないところで進んでいたインドとバングラデシュへの移民の解禁、これが日本国民に発覚して問題視されなければ、次にはネパールそしてスリランカと移民の解禁が続いていた筈だからです。
まあ、国との取り決めがなくとも、この噂を聞きつけたネパール人は、大挙して日本に向かってくる可能性もあるということです。
そもそも、ネパールという国は、出稼ぎ国家なので、随分前からネパール人は日本に移住しているのです。
そのネパール人は、一度、日本に入国したら母国には戻らないでしょう。
これでお判りの通り、ネパールでの暴動は、SNSの問題だけでなく、大量難民の発生にも繋がって行くことなので、日本も対岸の火事ではないということです。
下手すると、このネパールの窮状を見て、日本の売国奴の知事さん方がチンケナ正義感をひけらかせて人道支援で招き入れるかも知れません。
そうなれば、全国知事会の招きによって、地方のあちこちに、ネパール人村、インド人村、バングラデシュ人村、パキスタン人村が出来上がるのです。
頭のおかしな首長たちによって、左翼が喜ぶ日本の崩壊という断末魔は本当に始まってしまうかも知れません。
(※いつも慌てて書くので、誤字脱字が多く、何卒、ご容赦願います)

 忍者ライターの久保誠が「デュラルライフ」「田舎暮らし」「シニアライフ」「スローライフ」「海外ロングステイ」の情報と「雑学のすすめ」を主題として、ソフトタッチに日々の出来事、経済、国際情勢、政治、芸能、歴史のウンチクなどを語ってまいります。
忍者ライターの久保誠が「デュラルライフ」「田舎暮らし」「シニアライフ」「スローライフ」「海外ロングステイ」の情報と「雑学のすすめ」を主題として、ソフトタッチに日々の出来事、経済、国際情勢、政治、芸能、歴史のウンチクなどを語ってまいります。
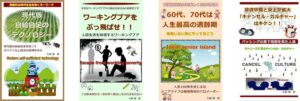
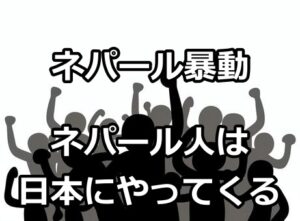


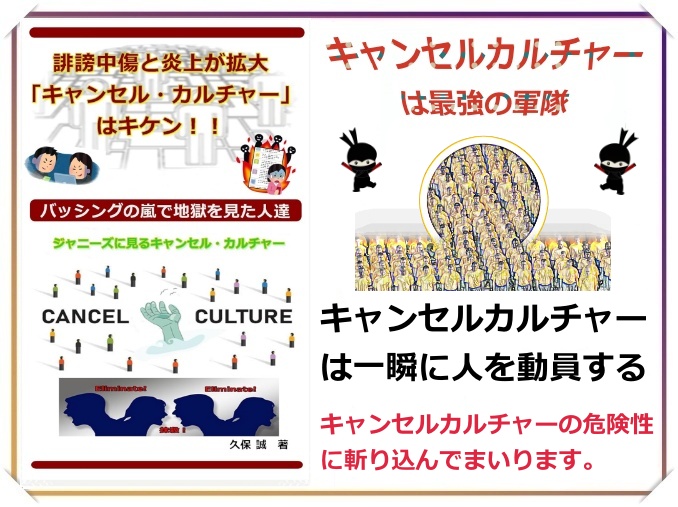
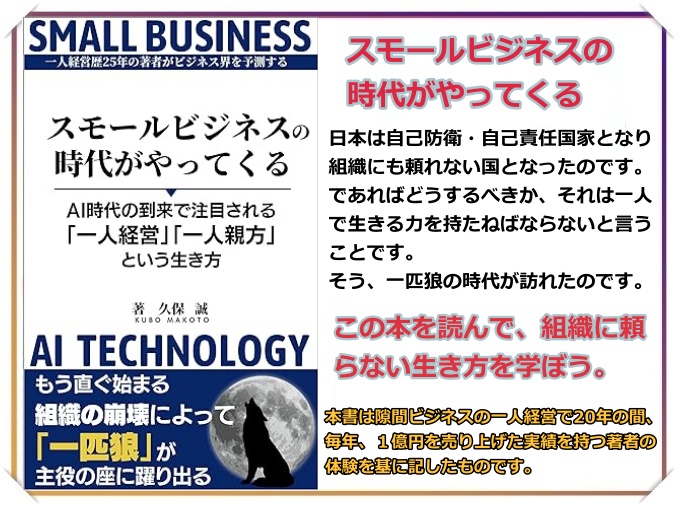

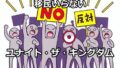
コメント